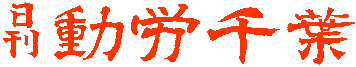検査周期延伸に関してJR東と団交
検修業務の将来展望について追及!
7月23日、動労総連合は、車両検修業務に関して、工場で行う保全検査を60万kmから80万kmに延伸するとの提案に関して、JR東日本本社との団体交渉を行い、周期延伸の根拠や今後の検修業務、基地のあり方等について追及を行ってきた。
工場の検査を20万km延伸
車輪摩耗で120万km?
組合 今回、検査周期の延伸を行う理由は何か。。
会社 今回、工場で行う指定保全、装置保全、車体保全を周期延伸の対象とした。
対象車種は近郊型はE231系以降、特急はE653系以降とし、指定保全の60万kmを80万km刻とし、各検査の周期を次のとおり延伸することとした。
指定保全 60万km→ 80万km
装置保全 120万km→ 160万km
指定保全 180万km → 240万km
車体保全 240万km → 320万km
運行している列車からテストカーを指定し、データをとり、各保全検査で周期を延伸しても問題がないかを検証した上で、部外の有識者の意見を踏まえ今回の延伸とした。
組合 テストカーの期間及び車種、編成数は。
会社 09年から15年まで行った。
231系 2600両の内、160両
233系 1200両の内、50両
531系 300両の内、40両、
721系 80両の内、6両
組合 テストカーの走行距離は。
会社 今回の周期延伸に踏まえ、プラス10万kmとし、指定保全で言えば80万km+10万kmまで走行し、検証した。
組合 部外の有識者とはどのような人物か。
会社 大学教授、国交省の外部機関である交通安全環境研究所、鉄道総研等の人たちである。
組合 80万kmとした根拠は何か。
会社 テスト開始時、首都圏でE231系、E233系の割合が増え、車軸の寿命を見た時に概ね160万km程度で取り替えが発生することを見据えて目標とした。
組合 走行する線区、速度、勾配等によって車輪の摩耗量は異なるはずだ。それでも160万kmまでもつのか。
会社 走る線区によって車輪の寿命は大きく変わる。ブレーキ時の制輪子や耐雪ブレーキ等の影響もあり、160万kmもつものもあれば、120万kmもたない線区もある。装置保全の160万kmまでもたない場合は、160万kmを超えない期間で装置保全を行うことになる。
組合 「概ね異常はなかった」とあるが。
会社 一部のテストカーで主電動機の異常が見つかった。軸受のグリスを分析した結果、鉄、銅の成分が基準値を超えていた部分があったので、「概ね異常はなかった」と記した。
組合 車軸が120万kmもたない場合、車両センターでの交換も考えているのか。
会社 車軸は、区所で行う前提ではない。
組合 周期延伸により、入場回数が減るが、工場の要員体制はどのように考えているのか。
会社 周期を延伸した分、将来的には要員が変化することはあり得ると考えているが、今すぐではない。
組合 対象車両が一巡するまでの期間は。
会社 5~6年かかると見ている。
「ミライの車両構創」ー車両基地及び労働者の将来をどうするのか?
組合 今回は工場関係の周期延伸だが、車両センターで行っている機能保全(月検査・年検査)、仕業検査への反映はどのように考えているのか。
会社 定期検査の考え方とした、工場での指定、装置、車体の各検査は、機器の寿命に応じて寿命を回復する検査になる。仕業検査、機能保全はその時々の車両状態を見るものである。今回、仕業検査、機能保全を変更する考えはない。
組合 現在、指定保全を行っている車両センターもあるが、広げる考えはあるのか。
会社 決まっているものはない。今後、基地の設備等を見直していく過程でそうした部分も出てくる可能性はある。
組合 今の回答で「設備の見直し」とあったが、今後の車両検修・車両センターのあり方について社員のタブレットに配信されているようだが、将来像についてどう考えているのか。
会社 社員への説明資料として「ミライの車両サービス&エンジニアリング構創」を示した。これからの車両メンテナンスがどうあるべきかを皆さんで考えていくということで現場の設備などもこれから良いものに替えていきたいという思いもあるし、職場も変わる可能性がある。今現在決まったものではないが、次の30年に向けて考えていくということだ。
組合 検修社員の将来はどのように考えているのか。
会社 今までのメンテナンスは、人が作業を行っていたが、その部分を最新の技術であるAIやロボットを使って検査できないかということを示した。検修業務は今後、235系等の自動で検査できる新しい車両・設備を導入して、ロボットで検査や清掃もできるような最新の技術・設備を入れながら行っていくという今後の検査のあり方、会社の方針を示したものだ。
組合 新しい車両基地なども検討していると聞いているが、基地の集約、車両の配置なども含めて考えているのか。
会社 車両センターも老朽化しているところもあり、新しく設置した方がいいのか、それに向けて新しい車両を配置していくのが適正なのかどうかも含めて判断しながら今進めている。この場で、どこの区所がどうなるかを示す段階ではない。
CBM導入で本線上からデータ送信ー検査は外観のみ?
組合 今後の新しい車両はCBMが必ずつける方向なのか。
会社 山手線の235系が基準になる。横須賀総武快速線も235系と同じような車両が入る。最新の技術を入れた新たな車両を入れていく。
組合 CBMを入れることによって現在の機能保全(月、年)の検査方法はどうなるのか。現在の検査方法を維持しながらCBMを活用するのか。
会社 二通りある。ひとつは、新保全体系の中で、一部の検査方法をデータに置き換えるというやり方。もうひとつは、235系でやっているモニタリング保全体系という定期検査の検査メニューから除き、全部、状態監視に置き換えているものもある。両方を平行で進めている。
組合 235系は、既存の機能保全(月、年)の対象から外れているのか。
会社 検査としては実施する。機能保全の最後の総合検査で運転台でハンドルを扱い、ブレーキ圧等を確認する。しかし、山手線では、運転士が扱えばリアルタイムで送信され、エラーが出ればアラートが鳴る。このアラートが鳴らない限り何もしない。90日に1回、基地に戻り、乗務員の扱いで見られない外観検査を検修社員が行っている。本線上から送られてくるデータで見られるものについては、車両基地に車両が入ってきても見ないという形をとっている。
組合 行うのは、消耗品交換程度か。
会社 それは残ってくる。あとは、人が目できる外観検査はまだ置き換えられていない。そういう部分も置き換えられないか技術開発等で勉強している。
グループ会社と水平分業ーJRに残るのは判断業務!
組合 「ミライの車両」の中で、JRとグループ会社で水平分業を行うとの記載があり、区別がなくなっている図がある。実際に働く労働者の立場はどうなるのか。
会社 グループ会社を一体でやっていくことはこれまでと変わらない。新しい車両を入れていく中で、人としてできる業務を今後も推進する。その中で、判断業務という形でグループ会社との業務をどのように棲み分けるかだ。
組合 判断業務はJR、具体的作業はグループ会社ということか。
会社 個々の作業の中で変わってくると思う。
組合 検修業務に関する要員確保、新規採用の考え方はどうか。
会社 メンテナンス部門は、車両に限らず電気、設備等かなり厳しい。その中で人材確保と働きやすい職場の確保を考えて採用している。
組合 会社の採用情報を見ると、事務職と技術職に分け、事務職に運転士車掌が入り、車両関係は「機械」に組み込まれているが何故か。
会社 一般の人から車両より機械の方が分かりやいとの声があった。
組合 この間、千葉では、幕張1名、京葉2名の配属であり、将来の技術継承という点でも厳しい。
会社 優秀な人材確保のためにやっていきたい。
組合 周期の延伸に関しては懸念している。また、今後の検修業務のあり方等についても議論を継続していく考えである。
会社 了解した。
以 上 |